災害薬事コーディネーターとは医薬品供給・薬剤師派遣に関する調整する役職
皆さんこんにちは!災害医療大学です!
災害医療・医療全般に欠かせないもの、って何でしょう?
医師や看護師のようなマンパワーは当然大切ですが、なんといっても「薬」がないと治療できません。
災害の現場や避難所、病院に薬を用意するのは、CSCAPPPの中のP「準備」「供給」に含まれているように薬剤師の役目です。
今回ありがたいことに、災害薬事コーディネーターの制度を設計された、静岡県薬剤師会の杉井 邦好 先生からお話を伺い、1つの講義としました!
静岡県薬事課の「ふじのくに 薬剤師シゴト大全」でも取材されています!
本講義は杉井先生に添削をしていただき、さらにコメントまでいただいています。
この場を借りて深く御礼申し上げます!
ぜひ最後までご覧ください!!
災害薬事コーディネーターとは?
災害薬事コーディネーター制度は、都道府県によって定められています。そのため、各都道府県によって異なる点があります。
今回は日本病院薬剤師会で報告された、熊本地震の際の災害薬事コーディネーターの活躍、静岡県医療救護計画などからまとめて紹介します。
災害薬事コーディネーターは災害時の医療救護活動に必要な医薬品・医療材料の確保、供給および、薬剤師の確保、派遣に関する業務の補完、実施を行います。
簡単に言ってしまうと、災害時に活動する薬剤師の調整役、みたいな形ですね!
現場で活動する薬剤師と対策本部をつなぐ役割を担います。
杉井先生からいただいた資料にわかりやすい図がありましたので掲載します!

災害薬事コーディネーターと災害医療コーディネーターの違い
災害薬事コーディネーターにかなり似ているものとして災害医療コーディネーターがありますね!
そもそも災害医療コーディネーターって何??という方はこちらの記事をご覧ください!
簡単にまとめると、災害医療コーディネーターとは、災害医療の総合調整を行う役職です。
つまり災害医療全体の指揮官です。
それに対して災害薬事コーディネーターは災害薬事の調整を行う役職です。
つまり、災害医療の中の薬に関する指揮官です。
違いはまだあります。
災害医療コーディネーターは国が定めており、厚生労働省が養成研修などを行います。
それに対して災害薬事コーディネーターは各都道府県にゆだねられています。
そのため、あくまでも地域主導で災害薬事コーディネーターの養成が進められています。
まとめるとこのようになります!
災害医療コーディネーター
災害医療の総合調整
国主体の導入と研修
災害薬事コーディネーター
災害薬事の調整
都道府県主導の導入と研修
災害薬事コーディネーターのきっかけ
なぜ災害薬事コーディネーターが必要なのでしょうか?
災害薬事コーディネーター制度を設計するにあたって何がきっかけとなったのでしょうか?
きっかけは「東日本大震災」です。
以前、東日本大震災の際の薬不足の真実を講義でまとめました。
簡単にまとめると、「支援医薬品はあるのに、仕分け管理ができず、医薬品ニーズに合わせられなかった」
→「現場における医薬品不足」→「大量の医薬品が残存」→「医薬品の大量破棄」
薬局の薬剤師を活用していれば・・・
支援医薬品は大量に届いていたが、仕分け管理や現場のニーズとのミスマッチにより、有効に使われず。
現場で必要とされる医薬品が届かず、大量の医薬品が残存し、結果的に廃棄せざるを得なかった。
現場が必要とする医薬品を要請し、仕分け管理を行い、現場に届ける仕組みが必要と考えました。
そのために薬局薬剤師を活用しようと考えました。
→これって普段薬局薬剤師がやっている仕事ですよね。
また、医薬分業の面から見てみましょう。
東日本大震災の起きた平成22年の全国の医薬分業率は63.1%。
令和2年の全国の医薬分業率は75.7%です。
つまり、地域における医薬品供給については東日本大震災の時よりも薬局の薬剤師の活用が重要になっています。
それを踏まえて、災害時には薬局間の、薬剤師同士の連携が重要!
→そのため、調整役を担う災害薬事コーディネーターが必要とされる
という流れですね!
実際のところ災害薬事コーディネーターは何をするの?
2011年の東日本大震災をきっかけに災害薬事コーディネーターが誕生した。と先ほど紹介しました。
つまり、災害薬事コーディネーターがかかわった災害としては2016年の熊本地震があげられます。
災害薬事コーディネーターの業務
災害薬事コーディネーターが行うことは以下のようになります。
- 仮設調剤所の立ち上げ
- モバイルファーマシーの設置場所の手配、撤収に向けての準備
- 支援薬剤師のスケジュール管理と割り振り
- 医薬品、備品等の急配の対応
- 被災地における薬剤師不足の現状把握と救援活動の必要性、派遣人数の検討
薬剤師が被災地で活動するための指揮官であることが明白ですね!
モバイルファーマシーとは
モバイルファーマシーとは「災害対策医薬品供給車両」のことです。
簡単に説明すると、「車型の動ける調剤室」です。詳しくはこちらの記事をご覧ください!
災害薬事コーディネーターはどのくらい必要か
イメージとしては災害医療コーディネーターとほとんど似ています。
静岡県の災害薬事コーディネーターは、
県本部の要員として県の災害対策本部、県の薬剤師会。
地域の要員として保健所、市町の災害対策本部、地域の薬剤師会に配置されます。
つまり、大規模災害の場合は地域の要員がたくさん必要になります。
具体的に何名必要か?は想定している災害の種類、規模、配置先によってきます。
災害薬事コーディネーターの制度は各都道府県にゆだねられているので、都道府県ごとの想定する災害に合わせて研修などが進められていくでしょう。
災害薬事コーディネーターの配置先は都道府県によって異なります。市町の災害対策本部に配置されるのは多分静岡県だけではないでしょうか?
7月3日の熱海市伊豆山の土石流災害の際には、熱海市災害対策本部に伊東熱海薬剤師会の災害薬事コーディネーターが入って、避難者や孤立地区への医薬品供給等に活躍しました。
災害薬事コーディネーターになるには?
基本的には薬局等の薬剤師としての職能に加え、災害時の医療救護に関する知識が必要になります。そのため、各都道府県では研修会が行われています。
都道府県によって制度が異なるため、各県の情報をご確認ください!
杉井先生からのコメント
今回なんと、災害薬事コーディネーターの制度を設計された杉井先生から、「災害医療大学で学ぶ皆さん」に向けてコメントをいただきました!
災害時の医療救護については、地域住民を守るための医療救護体制の整備(救護所等の設置、搬送体制の整備等)は市町村、市町村で対応できない広域的な医療救護活動(医師、薬剤師等の派遣調整、医薬品等調達・斡旋要請等)は都道府県と役割分担がされています。
つまり市町村が設置する医療救護所で必要な医薬品等は、市町村が調達することになります。しかしながら、市町村役場には政令市を除き薬剤師はいません。もし、市町村で調達できなければ、都道府県に要請することになります。静岡県災害薬事コーディネーターを創設する際に市町村への説明会を実施しましたが、多くの市町村では医薬品は県に要請すれば良いと思っていたようです。もし、仮に市町村から県への要請が殺到すれば、県の機能もマヒしてしまうことになります。石巻薬剤師会の方が東日本大震災の際になぜ医薬品が届かないのかを県庁に確認したところ、「要請がない」との返事だったとのことです。大規模な災害の際には市町村担当者には膨大な作業が生じ、手が回らないということも理解できますし、県の保健所も津波で被災しており機能不全になっていました。
静岡県でも大規模な災害が発生すれば、同じことが起こるだろうということは容易に想像でき、地域主導で医薬品等を確保できる体制整備の必要性を感じたことから、医薬品の調達・管理・調剤を常時やっている薬局薬剤師を活用する仕組みとして静岡県災害薬事コーディネーター制度を創設しました。
静岡県災害薬事コーディネーターの最大の特徴は、地域住民に最も近い所で医療救護を行う市町村の災害対策本部にも配置することになっていることだと考えています。令和3年7月3日に熱海市伊豆山で発生した土石流災害は記憶に新しいものであると思いますが、その際には熱海市災害対策医療本部に伊東熱海薬剤師会の災害薬事コーディネーターが入って、避難者や孤立地区への医薬品供給等に活躍しました。
話しは少し変わりますが、皆さんは富士山の中腹に宝永山があることを知っているでしょうか?宝永山は1707年に起きた富士山の噴火(宝永大噴火)でできたもので、その大きな規模と最も新しい富士山の噴火ということで知られています。宝永大噴火の49日前にはM8強の宝永地震が起き、死者2万人以上を発生させています。宝永地震は東海地震と南海地震の同時発生によって引き起こされたとされており、現在でも地震の発生が予想されている場所だけに、その再現が懸念されています。実は、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の4日後の2011年(平成23年)3⽉15⽇に富士山南麓でM6.4の地震が発⽣し、静岡県富⼠宮市で最⼤震度6強を観測しました。この時に私が一番心配したのは富士山の噴火です。世界的にみても大地震が発生すると活火山が噴火することが知られており、専門家もこの地震で富士山が噴火しなかったのは不思議だとコメントしています。
静岡県には富士山もあり、原子力発電所もあり、大規模地震が発生した場合には複合的な災害に発展する可能性もあります。災害に備えてマニュアルを作成しておくことは重要ですが、災害対応は必ずしもマニュアルどおりにはいきません。医療救護を必要としている人に適切な医療を届けるため、臨機応変に対応できる力をつける必要があると思います。
私が災害関連の研修会の最後に皆さんに伝えていることを災害医療大学で学ぶ皆さんにもお伝えしたいと思います。
・日頃からの訓練や研修は大事
・訓練はよりリアルに進化
・危機意識を常に持ち続ける
・想定外を想像する力をつける
災害医療大学で学ぶ皆さんが、災害が発生したときに活躍されることを期待しています。
本当に貴重なお話やコメントをありがとうございます!
本講義では、災害薬事コーディネーターとは何か?を紹介してきました。
災害医療大学では災害薬事に関する講義もいくつか公開しています。
ぜひ読んでみてください!







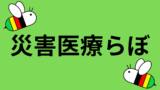
コメント